
葬儀の裏側って実際どうなってるの?
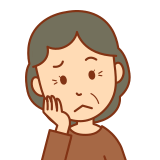
葬儀社は本当のところ何を考えてるの?
いつかはお世話になるだけに、気になりますよね。
通常では知りえない葬儀業界の真実と、賢明な選択のために知っておくべき重要なポイントを明かします。
本記事では、元葬儀社スタッフの視点から、費用の内訳、サービスの実態、そして後悔しない葬儀社の選び方について、具体的な事例を交えながら解説します。
葬儀社が明かす業界の実態と真実

葬儀社の基本的な収益システム
葬儀社の収益システムは、一般に考えられているよりも複雑です。
基本的な収入源は祭壇や棺などの商品販売、会館使用料、そして人件費です。特に祭壇装飾には50~60%という高い利益率が設けられており、業界の主な収益源になっています。
一方で、施設の維持費や人件費など固定費も高額です。24時間365日の対応を維持するのに、常時スタッフ確保の必要があり、これらのコストは安定した収益確保の理由の一つになっています。
表に出ない業界お決まりの実態
業界内では、いくつかの暗黙の了解が実在します。
地域の葬儀社同士での顧客の住み分けや、病院との連携における非公式な習慣などです。
特に、病院や老人ホームとの関係性は重要です。多くの葬儀社は、情報提供への感謝として、それぞれの関係者に定期的な挨拶回りを行っています。これは明確な規定があるわけではないですが、業界内では当然のお決まり事なのです。
葬儀社スタッフの本音と建前
現場で働くスタッフたちには、表向きには口にできない本音があります。
故人や遺族への真摯な対応を心がけながらも、業務の性質上、どうしても感情的な疲れを感じてしまうのです。
また、葬儀の規模や価格帯によって接客態度を変えては決していけないのですが、現実には売上目標のプレッシャーと、遺族への共感の間で葛藤を抱えるスタッフも少なくありません。特に経験の浅いスタッフの多くが、この 釣り合い を取るのに苦心しています。
一方で、本当にやりがいを感じる瞬間もあります。
遺族から「ありがとう」と言われたとき、故人の人生に寄り添える最後の機会に立ち会えることへの誇りも、確かに存在しているのです。
葬儀の裏側で起きている価格設定の仕組み

基本料金の内訳と隠れた費用
葬儀の基本料金には、一般的に知られていない内訳があります。
祭壇費用、会館使用料、人件費に加え、様々な管理費用が含まれています。特に注目すべきは、表向きの料金表に記載されていない「事務管理費」や「案内係費用」などの項目です。
実際の価格設定では、地域性や競合他社の料金体系を考慮しながら、利益率20~30%を目標に設定されるのが一般的です。ただし、この利益率は商品やサービスによって大きく異なり、祭壇や供花では利益率50%以上もあり得るのです。
追加オプションの真実
追加オプションには、実は大きな利益率が設定されています。
追加の供花や塔婆類は、原価の2~4倍の価格設定が一般的です。また、式次第や会葬礼状などの印刷物も、実際の制作コストと販売価格には大きな開きがあります。
しかし、すべての追加オプションが高利益ではありません。
例えば、会場装飾や司会者の手配など、外部への支払いが発生するサービスは、利益率が比較的低く抑えられています。
価格交渉の可能性と限界
価格交渉は、実は想像以上に余地があります。
特に、祭壇の規模や装飾、供花の数量などは、予算に応じて調整ができます。ただし、基本料金や人件費など、葬儀社の運営に直結する費用については、大幅な値引きは困難です。
交渉のポイントは、まず見積書の細かい内訳の確認です。
必要性があまりない付属サービスの見直し、祭壇の規模の調整で、総額を10~15%程度抑えれます。ただし、あまりに強引な値引き交渉は、サービスの質の低下につながる可能性があることも覚えておく必要があります。
もし、あなたの御身内で心配な方がいらっしゃるなら、一度葬儀社に、事前相談に行かれるのをお勧めします。
事前相談についての記事はこちらからどうぞ。
葬儀社スタッフが語る接客の舞台裏

営業トークの真意を解説
葬儀社の営業トークには、実は明らかな意図が隠されています。
「故人様の想いを大切に」「最後のお別れにふさわしい」といった言葉の背景には、より高額なプランへの誘導という目的があります。
しかし、すべての営業トークが売上重視というわけではありません。
家族構成や経済状況を考慮しながら、適切なプランを提案しようとする真摯な姿勢も見られます。
押し付け販売の実態
確かに一部の葬儀社では、強引な押し付け販売が行われています。
特に、故人や遺族の心理的な弱みにつけ込み、必要以上の商品やサービスを勧める例も見受けられます。
「他の遺族の方々はこちらのプランを選ばれています」「故人様への最後の供養ですから」といった心理的プレッシャーをかける発言は、計算された販売テクニックの一つです。
本当に必要なサービスの見極め方
実際に必要不可欠なサービスは、意外にもシンプルです。
具体的には、ご遺体の保管・処置、火葬手続き、そして基本的な式場設営などが中心になります。その他の多くのサービスは、実質的には選択可能なオプションなのです。
特に注意が必要なのは、高額な祭壇装飾や、過剰な供花、必要以上の参列者向けサービスです。これらは確かに見栄えは良いですが、実際の必要性を冷静に判断することが重要です。また、霊枢車や遺影写真などは、基本的なグレードでも十分な品質が確保されています。
知られざる葬儀社の選定基準と注意点

地域密着型と大手チェーンの違い
地域密着型の葬儀社は、地元のしきたりや習慣に詳しい知識があり、柔軟に対応してもらえます。
一方、大手チェーンは、標準化されたサービスと安定した品質が特徴です。価格面では、地域密着型が比較的割安な傾向にありますが、繁忙期の対応力は大手チェーンが優れています。
見積書の読み方と比較のポイント
見積書の比較では、基本料金の内訳を細かく確認することが重要です。
注目すべきは、祭壇費用、会館使用料、人件費の3点です。また、「管理費」「諸経費」といった曖昧な項目は要注意で、具体的な内容の説明を求める必要があります。
見積書の比較時は、単純な総額だけでなく、各項目の単価と数量のチェックが重要です。
例えば、人件費が1名あたりいくらで計算されているか、会館使用料に含まれるものは何かなど、詳細を確認します。
要注意な契約条件と確認事項
契約時には、特にキャンセル規定と追加料金の発生条件に注意が必要です。
多くの葬儀社は、契約後の変更やキャンセルに対して厳しい違約金を設けています。また、当日の急な変更や追加サービスは、割増料金が発生することもあります。
重要なのは、契約前に支払条件を明確にすることです。
例えば、支払時期や分割払いの可否、クレジットカード利用などを事前に確認します。また、予期せぬ事態に備えて、保険の適用範囲や料金の返金規定について確認しておくことをお勧めします。
葬儀の裏側から見える今後の業界動向

葬儀の簡素化と価格破壊の実情
近年、葬儀の簡素化が急速に進んでいます。
特に都市部では、家族葬や一日葬といった形式が一般化し、従来の価格体系が大きく変化しています。実際に、大手葬儀社の平均単価は下降の一途を辿っています。
急成長する新しい葬儀スタイル
オンライン葬儀やドライブスルー葬儀など、新しい葬儀の形式が登場しています。
これらは、コロナ禍を契機に普及が加速し、現在では持続的なサービスとして定着しつつあります。また、環境に配慮したエコ葬儀や、故人の趣味や個性を反映したオーダーメイド葬儀なども増加傾向にあります。
今後の業界変化への対応策
業界は大きな転換期を迎えています。
多くの葬儀社が、デジタル化への対応や、人材育成の強化を進めています。また、事前相談や終活支援といった、従来の葬儀執行以外のサービス展開も活発化しています。葬儀社の選択には、こうした新しい取り組みへの対応力も、重要な判断基準になってきています。
現代の葬儀に求められているのは、形式や規模ではなく、故人と遺族の想いに寄り添った、本質的な価値の提供です。今後は、このような価値観の変化に柔軟に対応できる葬儀社が、業界内でのシェア率を確保していくのではないでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。
