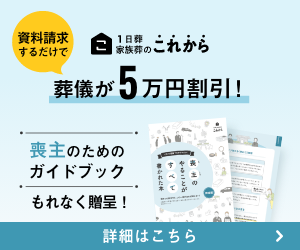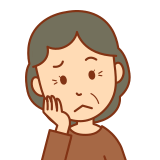
葬儀の費用って、どこまで相談できるの?

事前に準備しておけば、本当に抑えられるんだろうか・・・
気にはなるけど、なかなか家族間でも話題にしづらいですよね。
私は葬儀スタッフとして10年間で500件以上の葬儀に携わってきました。事前相談を行った方は、突発的な葬儀と比べて平均15〜20万円ほど費用を抑えることができます。
本記事では、現場経験に基づいた具体的な費用交渉のポイントや、実際にあった費用削減の成功事例を紹介します。
葬儀事前相談が必要な理由とメリット

葬儀の事前相談は、単なる費用対策以上の大きな意味を持っています。
突発的な葬儀と事前相談の費用差
突然の葬儀は、十分な検討時間がないので、必要以上の費用がかかってしまいます。私が経験した事例では、次のような費用差が生じています。
- 祭壇選択:事前相談では、複数のプランを比較検討できるため、平均で15~20万円の削減ができます。
- 返礼品:事前に数ある商品(値段も様々)をチェックしておくことで、最大で1セットあたり500~1,000円の削減ができます。
- 料理:こちらも量や質により値段にバラつきがあるので、適切な調整により、1人あたり1,000~2,000円の削減ができます。
実際の数字を見ると、事前相談を行った方は、突発的な葬儀と比べて平均15~20万円の費用削減に成功しています。
遺族の精神的・時間的負担が軽くなる効果
突然の葬儀では、遺族は大きな精神的負担を抱えながら、短い時間で多くの決断を迫られます。事前相談には、次のようなメリットがあります。
- 冷静な判断・・・感情的になりやすい当日ではなく、落ち着いた状態で検討できる。
- 時間的余裕・・・複数の葬儀社の見積もりを比較できる。
- 家族間での相談・・・重要な決定事項を、家族全員で話し合える。
- 不安の解消・・・専門家に相談することで、不明な点を事前に解消できる。
事前相談のベストなタイミング
「いつ相談に行けばいいのか」という質問をよく受けます。経験則から言えば、以下のようなタイミングがお勧めです。
- 65歳前後:まだ元気なうちに、自分の希望を伝えられる
- 親の介護を始めるとき:現実的な課題として考え始めるべき時期
- 入院している心配な方がいる。
私の経験上、最も多いのは、入院している心配な方がいるケースです。医師から余命宣告を受けてからでは、精神的・時間的な余裕がなくなります。また、突然の事故や急病に備えるためにも、元気なうちからの準備をお勧めしています。
事前相談で確認すべき3つの重要ポイント

葬儀の事前相談では、費用を抑える、確認すべき重要なポイントがいくつかあります。私が葬儀スタッフとして経験した中で、特に重要な3つのポイントをご紹介します。
基本プランと料金体系の確認
葬儀社によって料金体系は大きく異なります。基本プランには何が含まれていて、何が含まれていないのかを細かく確認しましょう。
葬儀の規模による費用の違い
一般的な葬儀の規模は、家族葬(10~30名程度)、一般葬(50~100名程度)、大規模葬(150名以上)に分かれます。規模によって式場の大きさや人員が変わってくるので、費用は大きく変動します。例えば、家族葬なら50~100万円程度、一般葬で150~300万円程度、大規模葬では400万円以上かかることも珍しくありません。
葬儀の規模を決める際は、故人のご希望や家族の意向はもちろんですが、会葬者の人数予測も重要です。実務経験から言えるのですが、予測より2~3割多めの人数で見積もっておきましょう。
必須項目と追加オプションの見極め方
基本プランに含まれる項目は、祭壇、棺、骨箱、仏具、遺影写真、受付用品などです。これらは葬儀に欠かせないものですが、グレードによって大きく価格が変わります。
一方で、追加オプションには、お料理、返礼品、追加の供花、高級な棺への変更などがあります。これらは必ずしも必要ではないですが、葬儀社からは「一般的です」と勧められることが多いものです。
私の経験上、追加オプションで費用が予想以上に膨らむケースが非常に多いです。例えば、供花の追加で5万円程度、お料理のグレードアップで1人あたり2千円程度の追加費用が発生します。
互助会の必要性
互助会は月々の掛け金を積み立てることで、将来の葬儀費用に備えができる制度です。ただし、加入する前に以下の点を必ず確認してください。
- 掛け金の総額と実際の葬儀費用との関係
- 解約時の返金条件
- 他の葬儀社での利用可否
- 物価上昇への対応方針
- 追加料金が発生する条件
特に注意が必要なのは、互助会に加入していても、ほとんどの場合、実際の葬儀時に追加料金が発生するという点です。私の経験では、互助会加入者のほぼ全員が何らかの追加料金を支払っています。
これらのポイントを事前に確認し、書面で残しておくことで、将来的な費用の上振れを防げます。見積書の細かい文字まで、必ず目を通すようにしましょう。
元葬儀スタッフが教える費用交渉の具体的方法
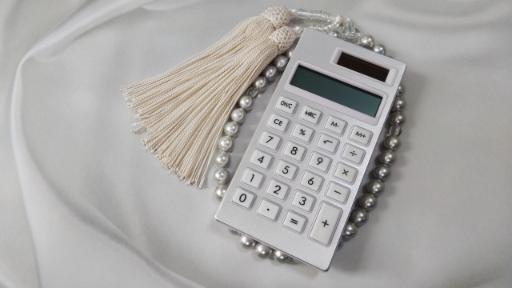
葬儀費用の交渉は、多くの方が不安に感じる部分です。10年間の現場経験から、効果的な交渉方法をお伝えします。
相見積もりの効果的な取り方
相見積もりは費用交渉の強力な武器になりますが、ただ複数の見積もりを取るだけでは効果は限られてきます。以下のポイントを押さえましょう。
- 3社以上の見積もりを取る(地域の大手と中小それぞれ)
- 基本プランの内容を細かく比較
- 各社の見積書の様式を統一して比較表を作る
- 見積書の有効期限を確認(通常3ヶ月~半年)
実務経験から言えることですが、「他社さんでこのような提案をいただいています」と具体的に示すことで、平均10~15%の値引きに成功するケースもあります。
値引き交渉で使える3つの具体的なフレーズ
特に効果的だった交渉フレーズをご紹介します。
- 「○○(具体的な項目)を外せば、価格はどの程度下がりますか?」
→ 項目ごとの価格交渉ができ、必要なものだけを選択できます。 - 「現在、複数の葬儀社で検討していますが、この価格であれば他社にお願いすることになりそうです」
→ 具体的な金額を示しながら交渉することで、価格調整の可能性が高まります。 - 「葬儀に有効期限があるのですか?急がしているみたいですよね。」
→ 有効期限延長で、値上げ後でも、見積もり金額での確約を得れるケースもあります。
状況により追加料金が発生しやすい項目
1.時間外の搬送代
・故人様を搬送するのが、夜中、早朝になってしまった場合は追加料金が発生します。
2.会館の安置室使用料・ドライアイス代
・通夜、葬儀が延びた際、会館に安置されている場合の安置室代、安置場所が会館、自宅問わずドライアイス代が一日ごとに追加されます。
私の経験では、安置室代は一日延びると約40,000円、ドライアイス代は約8,000円、追加になります。これらは事前に読めないですが、状況により発生するものなので想定しておいてください。
実際の葬儀事前相談の成功事例と費用削減額

葬儀スタッフとして関わった実際の事例をもとに、具体的な費用削減の方法と効果をご紹介します。
50代夫婦の事例|24万円の削減に成功
Aさん夫婦(50代)は、ご両親の葬儀に備えて事前相談に来られました。以下の取り組みで大きな成果を上げられました。
- 当初見積:230万円
- 削減後:206万円
- 削減額:24万円
具体的な削減ポイント:
- 祭壇のグレードを下げる(▲15万円)
- 返礼品の単価を下げる(▲5万円)
- 会館安置から自宅安置に変更(▲4万円)
注目すべきは、Aさんが「料理の質は下げたくない」という希望を伝えられたことです。優先順位をつけ、大切にしたい部分は確保しながら、全体の費用削減に成功されました。
70代単身の事例|31万円の削減を実現
Bさん(70代・単身)は、自身の葬儀について事前相談に来られました。
- 当初見積:150万円
- 削減後:119万円
- 削減額:31万円
具体的な削減ポイント:
- 家族葬プランへの変更(▲20万円)
- 供花の数量変更(▲5万円)
- 棺のランクを下げる(▲6万円)
Bさんの場合、「自分らしいシンプルな葬儀」という意向があり、それに沿った提案ができました。特に家族葬プランへの変更は、ご本人の希望と費用削減の両立を実現しました。
費用削減に成功した人の共通点
10年間で見てきた成功事例から、以下の共通点が見えてきました。
1.ゆとりの相談
- 時間のあるうちに準備を開始
- 複数の葬儀社と丁寧に相談
2・確かな優先順位
- 譲れない部分を明らかにする
- 費用を抑えられる部分を特定
3・徹底した情報収集
- 口コミやレビューのチェック
- 葬儀社の実績を確認
- 地域の相場観を把握する
4・詳細な記録
- 相談内容を必ずメモする
- 見積書の細かい内容まで確認
- 約束事項を書面にする
実際の削減額は、平均して当初見積もりの10~15%程度となっています。ただし、これは金額面だけでなく、納得のいく葬儀の実現という点でも大きな成果を上げています。
事前相談の具体的な進め方と注意点

最後に、相談の進め方と、見落としがちな注意点をお伝えします。
相談前の準備と必要書類
事前相談を効果的に進めるために、以下の準備をお勧めします。
1.基本情報の整理
- 希望する葬儀の規模
- 予算の目安
- 宗派や希望の形式
- 参列予定者数
2.確認資料
- 互助会や保険の加入状況
- お世話になっている寺院、神社等の情報
- 家族の連絡先リスト
互助会や保険の書類は、具体的な費用計算に必要となるため、必ず持参しましょう。
当日の質問リスト
以下の質問は、必ず確認しておくべき項目です。
1.基本的な確認事項
- 亡くなってすぐの対応連絡先とその後の流れ
- 基本プランに含まれるもの/含まれないもの
- 支払方法の選択肢
2.具体的な価格交渉
- パックプランのカスタマイズ
- 今後の経済情勢による価格変動
- 予算内に収まるよう追加オプションの調整
最後に

これまでの経験から一つアドバイスをさせていただきます。コロナ禍以降、葬儀業界は、急激な家族葬の普及により、一件あたりの売上は減少し、業界内の競争は激化しています。家族葬を対象とした安価なパックプランを前面に出し、オプションサービスで利益を得るスタイルが殆どです。
相談時の内容での見積もり書を作成してもらい、有効期限延長の有無も確認しておきましょう。「口頭での約束」は、担当者の異動などで取り消されてしまうかもしれません。
事前相談は葬儀の契約ではないので、固く考えないでください。状況や考えが変われば、何回でも見積りし直してもらえば良いのです。
事前相談は、決して重い話ばかりではありません。将来の不安を解消し、大切な方への最後の送り方を落ち着いて考えるきっかけになります。ご家族と相談しながら、納得のいく準備を進めましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
こちらおススメです