「近所の犬の鳴き声がうるさくて困っている…」「どうしたら騒音問題を解決できるのだろう?」そう悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
私自身も、数年前、悩んだ経験があります・・・当事者にしかわからないつらさも味わいました。
しかし今思えば、近所の犬の鳴き声問題は、適切なアプローチと飼い主との話し合い、コミュニケーションで、ほとんどのケースで解決できることもわかりました。
この記事では、近所の犬の鳴き声トラブルを解決する5つの具体的な対処法と、飼い主との良好な関係を維持しながら問題を解決するのポイントを解説します。
近所の犬の鳴き声がうるさい原因と基本的な対処法

犬が過剰に吠える一般的な理由
犬が頻繁に吠える背景には、様々な理由が有ります。最も一般的なのは、不安やストレス、退屈さからの反応です。特に、飼い主が長時間不在や、十分な運動ができていない場合に多く見られます。
また、縄張り意識からの警戒吠えや、他の動物や人への興奮による吠え声も代表的なものです。犬は本能的に自分の縄張りを守ろうとする習性があり、見知らぬ人や動物が近づくと警戒して吠えることがあります。
飼い主が取るべき基本的なしつけ方法
適切なしつけは、過剰な吠え声を抑える上で重要です。基本的なアプローチとして、以下の3つが効果的です
- 十分な運動と遊びの時間を作る
- 規則正しい生活リズムを作る
- 吠えない時を褒めて向上させる
大切なのは、犬が静かにしている時はとにかく褒めましょう。これにより、望ましい行動を学習させることができます。
近隣トラブルに発展する前の初期対応
問題が大きくなる前に、まずは状況を客観的に記録しましょう。
- 吠える時間帯や継続時間をメモする
- できれば動画や音声で記録を残す
- 他の近隣住民の反応も確認する
これらの記録は、後々飼い主との話し合いや、必要に応じて行政に相談する際の重要な資料となります。
早期発見・早期対応が、近隣トラブルを防ぐ鍵となります。過剰な吠え声に気づいたら、まずは冷静に状況を観察し、記録しましょう。この段階での適切な対応が、後のスムーズな問題解決につながります。
私の体験談

うるさい!犬ってこんなに鳴くものなの
私が悩まされた犬は、我が家の斜め後ろの家でした。
ある日突然、飼い主が朝、仕事に出て行ってから夕方帰宅するまで、甲高い犬の鳴き声がするようになり、連日8時間ぶっ通しで鳴いていました。
いくら昼とは言え、平日毎日この状態なので、仕事をせずに在宅が多かった私にはとても辛いものでした。暑くても窓も開けず締め切ったままですし、体調が悪い時も寝むれません。うるさいので友人に遊びにも来てもらえません。
主人に話しても、飼い主が在宅している土日は鳴かないので、私が神経質なだけといまいち相談にも乗ってくれず、孤立してしまいました。
今思えば、精神的にかなり追い詰められた状態だったと思います。
誰もわかってくれない・・・
家が斜め後ろでしたので、お付き合いは無く住んでいる方がなんとなくわかるという程度でした。
他にも鳴き声が気になってる方がいると思ったのですが、犬を飼っているお家の前後左右、斜めも日中は仕事で出られている状況でした。ですので、心底苦痛を感じているのは私だけ・・・
突発的に保健所に電話をして、注意をしてほしいとお願いしました。後日調査に来てくれたのですが、ちょうど飼い主が帰宅したぐらいでしたので、鳴いておらず騒音は無いという結果に終わりました。
精神的に追い詰められていた私は感情的になってしまい、記録もおろか状況をも冷静に伝えられてなかったのかもしれません。
近所のことなので、言いたくはなかったのですが、思い切っての班長さんに、定例会で議題に出してもらうようにお願いしました。が、しかし議題というほどの扱いもされず、議事録の一行程度に小さく書いてあるのみで、各戸ほとんど見られていない回覧板として回されただけでした。
自治会としてはこれ以上はできない、当事者同士で解決して下さい。という回答です。
助け舟が来た!
我慢の限界の中、同じ並びの家で自治会でいろんな役をされている方が、助け舟を出して下さりました。自治会では名の知れた方で、同じ班だった私のことも知って下さってました。
飼い主の方も勿論知ってらっしゃって、鳴き声で困っている家があると上手にお話しして下さったのです。
飼い主の方も留守の間鳴いているのは、うすうすわっかてはいたようです。ミニチュアダックスを庭でつないで留守番をさせていたので、さみしかったのかもしれません。これ以降は留守番も室内になったので、たまに鳴く程度になりさほど気にならなくなりました。
あの時、お話して下さった方には感謝の気持ちで一杯です。それとともに、ご近所付き合いの大切さを身に染みて実感しました。
私はかなり遠回りをしましたが、適切なアプローチと継続的な記録、事前の根回しをすればもっと早く解決できたのです。
飼い主への効果的な伝え方とコミュニケーション方法

最初の声かけのタイミングと方法
飼い主との最初の接触は、問題解決の成功、失敗を左右する重要なポイントです。
理想的なタイミングは、犬の鳴き声が落ち着いている平日の夕方か週末の昼間です。突然の訪問は避け、出来れば事前に手紙やメモを投函してお会いしたい日の希望を伝えることをお勧めします。
トラブル回避のための会話のポイント
効果的なコミュニケーションの秘訣は、以下の3点を意識することです。
- 問題を一方的に非難せず、自分の状況を客観的に説明する
- 飼い主の立場も考慮し、一緒に解決策を探る姿勢を示す
- 具体的な解決案を提案する
決して、感情的にならずに冷静な態度を維持しましょう。多くの飼い主は、適切なアプローチで協力的な態度を示してくれます。
要望を伝える際の具体的な文例
効果的なコミュニケーションには、以下のような表現を活用しましょう。
【良い例】
「お話させていただきたいことがあるのですが、お時間はありますでしょうか」
「私も動物が好きなのですが、最近、夜間の鳴き声が気になっていまして…」
「何かお困りでしたら、私にもできることがあるかもしれません」
【避けるべき例】
「いつまで放っておくつもりですか」
「なんとかしてください」
「警察に通報しますよ」
前向きな対話を心がけ、互いの立場を尊重しながら、具体的な解決策を探っていきましょう。
法的対応と行政への相談方法
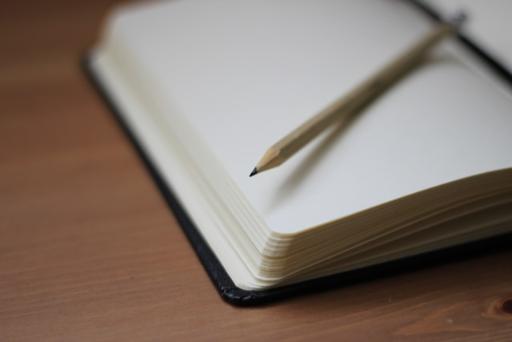
騒音に関する法律と規制
騒音問題(犬の鳴き声)に関する規制は、各自治体の条例が重要な根拠となります。一般的に、継続的な犬の鳴き声が60デシベルを超える場合、生活騒音として規制対象となります。
自治体窓口・動物愛護センターへの相談手順
自治体窓口・動物愛護センターへの相談は以下の手順で行います
- 問題の具体的な状況を記録(日時、頻度、継続時間)
- 電話での事前相談
- 必要に応じて現地調査の依頼
- センターからの飼い主への指導要請
相談の際は、これまでの飼い主とのコミュニケーション履歴も重要な情報となります。
警察への通報が必要なケース
警察への通報は以下の場合に検討します
- 深夜早朝の著しい鳴き声が継続
- 飼い主が改善の申し入れに全く応じない
- 威嚇や脅迫など、二次的なトラブルが発生
警察への通報は最終手段として下さい。
長期的な解決に向けた地域コミュニティでの取り組み

町内会・自治会での問題共有方法
町内会で効果的に取り上げてもらう
- 個別案件ではなく、ペット飼育全般の課題として提示する
- 実際の騒音データや近隣からの声を匿名で共有する
- 定例会議での提案と事前の根回し
地域でのペット飼育のルール作り
具体的なルール作り
- 飼い主・非飼い主双方の意見収集
- 基本的なガイドラインの作成
- 地域の実情に合わせたルールの調整
- 定期的な見直しと更新
飼い主同士の交流促進策
コミュニティ形成のための施策
- ペットのしつけ教室の定期開催
- 飼い主交流会の実施
- 地域のペットマナー向上キャンペーン
- SNSグループでの情報共有
これらの取り組みを通じて、長期的な問題解決と良好な地域関係の構築を目指します。
まとめ

近所の犬の鳴き声問題は、段階的なアプローチで解決ができます。まずは犬の吠える原因を理解し、飼い主との協力的なコミュニケーションを心がけましょう。対話での解決が難しい場合は、行政への相談や法的対応を検討します。
最終的には、地域コミュニティ全体の取り組みで、長期的な解決を目指すことがベストな選択となります。
このように多方面からのアプローチが、近隣関係を維持し、より良い住環境を実現しているのです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
